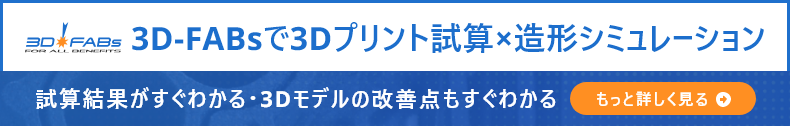皆さんは覚えていますか? 約10年前に「3Dプリンター」ブームが起きたことを。当時、3Dプリンターを扱う企業が増えて、自分や家族などのフィギュアを作るサービスが流行っていたなあ…なんてことを思い出します。
ところが最近、さまざまな業界のものづくりで「3Dプリンターの活用が進んでいる」というニュースをよく目にするようになりました。なぜ3Dプリンターが再び話題に? かつてのクオリティの印象が強く、正直ビジネスでの活用が想像しにくいのですが、10年前からどう進歩しているのでしょうか。
そのような疑問を解き明かすべく、私、ライター松山が、オリックス・レンテック 東京技術センター内にある「Tokyo 3D Lab.」を訪問。3Dプリンターの「今」を確かめてきました!

航空機の部品やインプラントも!? 加速する3Dプリンターのビジネス活用

はじめまして! ライターの松山です。今日は3Dプリンターの「今」について、いろいろ教えてください! 3Dプリンターは素人ですが、気になっていることを率直にお聞きしたいと思います。


ようこそ! 3Dプリンター事業推進チームでリーダーを務めている袴田です。

チームメンバーの安田です。本日はよろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします! 早速ですが、最近ネットニュースなどで3Dプリンターの話題を見かけることが増えた気がします。なぜ今、再び3Dプリンターが注目を集めているのでしょうか。


製品開発のスピードアップや、生産プロセスの柔軟性を高めるために、今、製造業を中心に、さまざまな業界で3Dプリンターの導入が進んでいるんです。国内では、主に開発部品の試作や、生産ラインで使われる治工具の制作に活用されていることが多いですね。金型を作らずにものづくりができるため、部品などの最終製品を少量生産する場合などに、3Dプリンターを用いるケースもあります。

欧米諸国や中国では、飛行機や自動車の部品、医療用のインプラントなどを3Dプリンターで作っている例もありますよ。

飛行機の部品って、かなり高度な品質基準が求められますよね。そんな部品も3Dプリンターで作ることができるんですか!
日本人の多くが、「スペックの低い3Dプリンター体験」で止まっている可能性が

でも、3Dプリンターって、そんなに精巧にモノを作れるイメージがないんですが…。


それはおそらく「一般コンシューマー向け3Dプリンター」の印象が強く刻まれてしまっているからかもしれませんね。

ほほう…?

3Dプリンターは、いわゆるローエンドモデルの「一般コンシューマー向け3Dプリンター」、そしてハイエンドモデルの「業務用3Dプリンター」と、大きく2種に分類されるんです。前者はご家庭や趣味などにお使いいただくもの、後者は、事業などビジネスで活用することを想定したものになります。

約10年前のブームでは、3Dプリンターへの期待が急速に高まった結果、比較的手頃なローエンドモデルが一気に社会へ普及したんです。ただ、あくまで「家庭用」のスペックとなるので、事業に耐えうる精度ではなく、失敗も多々起きました。
例えば、夜にセッティングした3Dプリンターが、翌朝こんな状態になっていた経験をお持ちの方も多いはずです。


これ、どういう状態ですか?

ノズルが詰まってしまったんですね。3Dプリンターは基本、材料を積層して造形していくのですが、ノズルが詰まると、ずっと空打ちしていたり、欠損が生じたり、このように糸が絡まったような状態になったり。そうした不具合がローエンドモデルでは起きやすいんです。

朝起きてこの状態は凹みますね…。

ブームが起きた際、「まずはローエンドモデルで試そう」とされた企業が多かったのですが、ご説明したとおりローエンドモデルのスペックには限界がありますから、結局「全然使えない…」という印象が根付いてしまったのが実情ではないでしょうか。

日本の3Dプリンターの市場シェアは約8割がローエンドモデルです。価格やノウハウが無いことなどが壁となり、多くの方の3Dプリンターの性能に対する認識が「家庭向け」に留まっている可能性がありますね。

事業に活用するなら、ハイエンド3Dプリンターを!

なるほど…。ところで、ハイエンドモデルとローエンドモデルって、具体的にな性能は、どんな違いがあるんですか?

そうですね…大きく4つのポイントがあると思います。1つ目は造形方式の選択肢の広さ。
そもそも、3Dプリンターには7つの造形方式があります。長くなるので、それぞれの方式の説明は割愛しますが、用途に合わせて適切な造形方式を選ぶことが大切なんです。用途とは、例えば強度を高めたいのか、表面を滑らかにしたいのか、造形スピードを早めたいのか、などですね。
ローエンドモデルは7つの造形方式のうち1〜2つの方式しか対応していないので、用途に合う方式を選べないケースが多いのです。例えるなら、「スポーツカーを走らせたいのに、商店街の道しかない」といったイメージでしょうか。

それは…確かに走りづらい感じがしますね(笑)。


2つ目は、「温度管理」の有無があります。3Dプリンターの造形する箱をチャンバーと呼ぶんですけど、ハイエンドモデルはチャンバー内の温度を調節できるんです。

温度を調節できると何が良いんですか?

一般的に温度を上げたほうが、造形物の変形が少ないと言われています。ローエンドモデルは温度管理ができないので、フィラメントと呼ばれる金属や樹脂でできた材料を溶かす過程で、うまく溶けなかったり、造形物が反り上がってしまったりすることがあるんです。


そして3つ目は、使える材料ですね。ローエンドモデルは使用できる材料に制限があるのですが、ハイエンドモデルであれば、金属や、スーパーエンプラという耐熱性や機械的強度に優れた高機能樹脂など、さまざまな材料を使うことができます。

つまり、いろんなものを作れるということですね。


そのとおりです。最後の4つ目は、造形サイズの違いですね。ハイエンドモデルの中には1m幅のモノを作れるような装置もあります。そうすると、大きな造形物にも対応できますし、チャンバー内に収まるサイズのもの、かつ同じ材料であれば、同時に複数作れるので、生産性や開発スピードにも差が出てきます。

ピザ窯のサイズが大きいほど、同時に焼ける枚数が増えますし、違う種類のピザも一緒に焼けますよね。そんなイメージです。


先ほどから、たとえが分かりやすい…!

ありがとうございます(笑)。なので、ハイエンドモデルとローエンドモデルの違いをひと言で表すならば、「作れるものの品質が桁違いである」ということですね。

なるほど、ハイエンドモデルとローエンドモデルの違いはよく分かりました。でも、もちろん価格も違うんですよね?

私たちは、100万円以下の3Dプリンターをローエンドモデルと分類しています。だいたい10万〜50万円の価格帯のものが多いですね。
ハイエンドモデルもピンキリですが、素材に金属を使えるものだと1〜2億円ぐらいします。

…億! よほどお金に余裕のある企業じゃなければ、導入できないじゃないですか。
3Dプリンターを活用する上での一番の課題は、使いこなすための技術やノウハウの不足

おっしゃるとおりです。そのために、オリックス・レンテックでは3Dプリンターに関するさまざまなサービスをご提供しています。
まずは、造形を受託する「3Dプリンター出力サービス」。お客さまに3Dデータをご用意いただき、私たちが複数保有している業務用3Dプリンターを活用して造形品を作り、納品させていただくというサービスです。


なるほど。それなら気軽に試せそうですね。

はい。あとはお客さまが装置を占有してご活用いただける「サブスクリプションサービス」、装置を一定期間お貸しする「レンタルサービス」もご用意しています。また、3Dプリンター導入に向けて素材ごとの作業工数や安全性、必要と技術力などの検証を行える「導入支援サービス」もご提供しています。

なるほどー。やりたいこととか予算に合わせ、いろんな装置の使い方が相談できるんですね。頼もしい!
でも正直、自分が作りたいものがハイエンドの3Dプリンターで実現できるのか、ちょっと分からないです。

そうですよね。実は3Dプリンターを活用する上で一番の課題とされているのが、使いこなすための技術やノウハウ不足なんです。「そもそもこれは、3Dプリンターで作れるの?」という疑問はもちろん、お客さまが持っている装置で実際に作ってみたけど、うまく作れないといったお悩みをよく伺います。
なぜ失敗したのか、原因が分からない。「仕方ないから外注しよう」と思っても、各社いろんな装置やメニューがあって、どこに頼むのが良いのか分からない。そのような課題が、3Dプリンター活用の障壁になっていると感じます。

巷では3Dプリンターがけっこう話題になっているし、進化してるっぽいのでいろいろ作れそうな気はするんだけど、自分に知識やノウハウがないから手を出せないという…。

はい、私たちも全国各地のお客さまから3Dプリンターについてのお問い合わせが増える中で、根本的なところからサポートさせていただくことが必要と感じていました。そこで、2023年5月に、『学べる見積サイト・3Dプリントソリューション「3D-FABs」』を立ち上げたんです。

なんですか、それ?

お客さまの設計データをアップロードしていただくことで、Web上でAIを使ったシミュレーションを行いながら、3Dプリンター活用に必要なノウハウを蓄積することができる「学べる見積サイト」です。
装置や材料などを選び、その場ですぐに概算費用や納期なども把握できるんですよ。

お、なんだか面白そうなサービスですね。詳しく教えてください!
(次回に続く)